前回紹介したBurgandy Street Bluesとならぶ、ジョージ・ルイスの十八番、世界は日の出を待っている(The World Is Waiting for the Sunrise)は、かつて世界中のディキシーランド・ジャズの楽団が盛んに演奏した曲。この曲は、もともとカナダのクラシック系ピアニスト兼指揮者のジーン・ロックハートとその友人であるアーネスト・サイツが合作した歌曲であったといわれている。第一次世界大戦当時に流行したポピュラー曲で、その後、ニューオリンズ・ジャズバンドのスタンダードとなり、後にはベニー・グッドマンやレス・ポールもこの曲を録音している。ジョージ・ルイスのコンサートでは、必ずこの曲が採り上げられている。
東京公演でも(前回紹介のCD)でも、この曲が始まると、待ってましたとばかりに観客から声がかかり、大変な盛り上がりを見せた。ジョージ・ルイスのアルバムで、一時幻の名盤といわれた、1954年3月3日のオハイオ州立大学でのライブレコーディングアルバム、Jass At Ohio Unionでも、この曲が始まると、会場全体に熱気が漂い、素晴らしい演奏を披露された。特に、バンジョーのローレンス・マレロが素晴らしかった。
このオハイオ・コンサートは、会場全体にただならぬ熱気が漂い、当時のジョージ・ルイスバンドの巡回コンサートへの大変な歓迎ぶりが伺える。この時は、ロサンジェルスから東部までの長い巡業のなかの途中であったらしい。1954年のコンサートであるから、ニューオリンズ・ジャズ誕生から数えると、既に半世紀ほど経過しており、決して時代の先端ではなく、どちらかといえばトラッドな過去の音楽であるにも関わらず、観客は同時代的なリアリティのなかでこのバンドの演奏を存分に楽しんでいたように思える。
ジョージ・ルイスをはじめ、各プレイヤーと、観客が一体となり、会場を興奮のルツボに巻き込んだこの日のライブの熱気は、レコードを通してこちらの方までダイレクトに伝わってきた。LPレコード2枚組のボックスセットから1枚目のレコードを取り出したときは、最後まで聴く気はなかったのだが、針をおろした瞬間から惹き込まれ、2枚目の終わりまで一気に聴いたのを覚えている。
このアルバムを聴いて、ニューオリンズ・ジャズというのは、ワイルドでラフで俗っぽくて、時には崇高ともいえる音楽だと思った。人間の喜怒哀楽がすべて含まれ、これほど各プレイヤーが理屈抜きで生き生きと音楽を奏でられるということが自分には驚きであった。ドラムスのジョー・ワトキンスのヴォーカルは、南部なまりで、洗練されておらずワイルドであるが故に文句なしの説得力を持つ。地域色が豊かであるからこそ、誰もが新鮮に感じるのだ。トロンボーンのジム・ロビンソンは、Ice Creamで迫力満点のソロを見せる。バンジョーのローレンス・マレロも大活躍。
ニューオリンズ・ジャズは、かつてはローカル音楽だったのが、ラジオ、レコードなどにより1930年代の終わり頃から、アメリカ中に知れ渡るようになった。そして一大センセーションを巻き起こした。いわゆるニューオリンズジャズ・リバイバルだ。戦後も、このジョージ・ルイスのオハイオコンサートに例をみるように、ジョージ・ルイスらの全米ツアーにより多くの感動を与え、人気は衰えなかった。また、ヨーロッパでもブームが起きた。60年代には、日本でもツアーが行われ、多くの人々にディキシーランド・ジャズの魅力や楽しさを教えてくれた。しかし、1968年12月31日にジョージ・ルイスは亡くなる。本当のニューオーリンズジャズバンドの終わりであった。(Djangoより)
※参考文献:河野隆次: JASS AT OHIO UNION(BMC-4032〜33) LPレコード ライナーノート
◇◇◇
※このアルバム(JASS AT OHIO UNION 徳間ジャパン)は、2000/3/16にリリースされましたが、新品は入手困難です。


 残念ながら、彼は1955年に亡くなり短命に終わっている。だから、作品の数は少なく、それほど知名度も高くなかった。しかしそのアドリブは一度聴くと忘れられないほどの魅力を持ち、聴き手を引きつける。フレーズが自然でなめらかだ。しかも、フレーズの間(ま)が絶妙で、全く抵抗なく聴き続けられる。こちらの耳が、積極的にアドリブ展開を聴き逃さないように追いかけるようになる。ソニー・ロリンズ出現以前では、最もよく歌うモダンテナーだとも言われている。チェースのアルバムでは大和明さんがライナーノートを担当。岡崎正通さんとの共著モダン・ジャズ決定版で、氏は以下のようにワーデル・グレイを絶賛している。(Djangoより)
残念ながら、彼は1955年に亡くなり短命に終わっている。だから、作品の数は少なく、それほど知名度も高くなかった。しかしそのアドリブは一度聴くと忘れられないほどの魅力を持ち、聴き手を引きつける。フレーズが自然でなめらかだ。しかも、フレーズの間(ま)が絶妙で、全く抵抗なく聴き続けられる。こちらの耳が、積極的にアドリブ展開を聴き逃さないように追いかけるようになる。ソニー・ロリンズ出現以前では、最もよく歌うモダンテナーだとも言われている。チェースのアルバムでは大和明さんがライナーノートを担当。岡崎正通さんとの共著モダン・ジャズ決定版で、氏は以下のようにワーデル・グレイを絶賛している。(Djangoより)


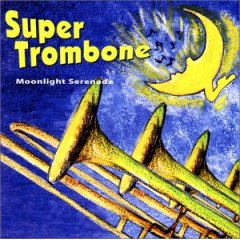

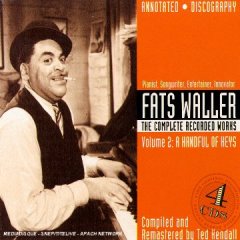





最近のコメント